『世に棲む日日』と時勢論
世の中の動きが、幕末の様相を呈してきています。
そこで、司馬遼太郎が吉田松陰と高杉晋作の生涯を通じて幕末を描いた『世に棲む日日』より、名言をピックアップしてみました。
一巻はまだ長州藩が風雲に飛び込む前なので、二巻から紹介させて頂きます――。
Image may be NSFW.
Clik here to view.
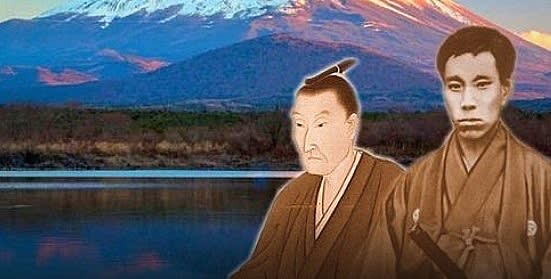
世に棲む日日(二)
【民族的自尊心】
吉田寅次郎も駈け回った。かれの主張は、仲間の他の書生たちと同様、
――断乎(だんこ)、屈するなかれ。
といういわゆる攘夷論であった。
そのくせかれらは鎖国主義者ではなく、要するに強要されて屈服するというのは、一国一民族の恥ずべき敗北であり、ここで屈服すればついにこの民族は自立の生気をうしなうであろうというものであった。
この異常に強烈な民族的自尊心をもりあげたかれの理論は、やがてその後の志士たちの思想に重大な影響をあたえてゆくのだが、この松陰理論ができあがる発酵のたねに、松陰個人としての自尊心のつよさがあるであろう。
【一大事件】
晋作は最後までだまって聞いていたが、やがて痰を切るような勢いで、「久坂、議論では幕府は倒れんぞ」と言い、いま停頓している情勢を旋回させるには一大事件が必要なのだ、その事件のためにわれわれは死ぬ、それがわからぬようであれば久坂の学問も屁のようなものだ、と戦略的立場から言い、「これ以上愚論をいうなら斬るぞ」と言った。
【特異な政治的緊張】
日本は、この列島の地理的環境という、ただひとつの原因のために、ヨーロッパにはない、きわめて特異な政治的緊張がおこる。
外交問題がそのまま内政問題に変化し、それがために国内に火の出るような争乱がおこり、廟堂(政府)と在野とが対立する。
【幕威のおとろえ】
幕威が、おとろえた。
幕威のこの急速なおとろえは、嘉永6年ペリーがきたときからのことで、この節目の明瞭さも、この国の特殊な地理学的理由に根差している。
ペリーで代表される外圧さえなければ、幕府の権力生理の寿命はあと半世紀はたっぷり保ったであろう。
【悔幕】
「幕府とは、たかがそれだけの力か」ということを、一瞬で士民は知った。
それまで300諸侯以下は、他に比較する勢力がないために徳川幕府の権力を絶対視し、その権力は天地とともにあるとおもい、さらに天地とひとしく盛大なものであるとおもいこんでいたのが、一瞬で醒めた。
「その程度か」ということが、悔幕になった。
【悔幕現象】
憂国的な諸侯は、それでまでは江戸城を神殿のように畏れていたのに、この一瞬以後は堂々と出入りし、それまでは禁忌であった幕政批判を堂々と老中の前でやった。
(中略)
ついでもうひとつの悔幕現象は、それまで幕府に対してなんの発言権もなかった今日の朝廷ー公家ーが、居丈高になって幕府の外交的弱腰を痛罵しはじめたことであった。
【独立性の賛美】
井伊直弼が天下に君臨した絶望の時期にあって、萩にいるかれのフラスコのなかの思想は、ほとんど蒸留水のように純粋になり、
「独立不羈(ふき)三千年来の大日本」
と、日本の独立性を賛美し、その日本をアメリカの束縛下におくことを、
「血性ある者、視るに忍ぶべけんや。ナポレオンを起こしてフレーヘード(自由)を唱へねば腹悶医(いや)しがたし」 とさけぶようになった。日本史上最初の革命宣言というべきであろう。
【草莽(そうもう)の蜂起】
松陰はこの時期、公家にも絶望し、大名もたのむべからず、ついに救国の革命事業はそのような支配層よりも革命的市民(草莽)のいっせい蜂起によってとげざるをえないとおもうようになった。
【三種類の人間群】
革命の初動期は詩人的な予言者があらわれ、「偏癖」の言動をとって世から追いつめられ、かならず非業に死ぬ。松陰がそれにあたるであろう。
革命の中期には卓抜な行動家があらわれ、奇策縦横の行動をもって雷電風雨のような行動をとる。高杉晋作、坂本竜馬らがそれに相当し、この危険な事業家もまた多くは死ぬ。
それらの果実を採って先駆者の理想を容赦なくすて、処理可能なかたちで革命の世をつくり、大いに栄達するのが、処理家たちのしごとである。伊藤博文がそれにあたる。
松陰の松下村塾は世界史的な例からみてもきわめてまれなことに、その三種類の人間群をそなえることができた。
【乱世の雄】
晋作は久坂という者を乱世の雄とはおもえず、治世にあって廟堂のぬしになる男だとおもっていた。
いまの世に必要なのは廟堂の才ではなく、馬上天下を斬り従える才であろう。晋作はひそかに自分こそそれであると思っている。
【思想論】
思想というのは要するに論理化された夢想または空想であり、本来はまぼろしである。
それを信じ、それをかつぎ、そのまぼろしを実現しようという狂信狂態の徒(信徒もまた、思想的体質者であろう)が出てはじめて虹のようなあざやかさを示す。
思想が思想になるにはそれを神体のようにかつぎあげてわめきまわる物狂いの徒が必要なのであり、松陰の弟子では久坂玄瑞がそういう体質をもっていた。
要は、体質なのである。松陰が「久坂こそ自分の後継者」とおもっていたのはその体質を見ぬいたからであろう。
思想を受容する者は、狂信しなければ思想をうけとめることはできない。
【思想家と現実家】
晋作は思想的体質でなく、直感力にすぐれた現実家なのである。
現実家は思想家とちがい、現実を無理なく見る。思想家はつねに思想に酩酊していなければならないが、現実家はつねに醒めている。
というより思想というアルコールに酔えないたちなのである
【真の強者】
世間は騒然としてきている。長州の下級武士たちも動揺しはじめていた。
晋作はそういう風雲のなかに身を投ずるか、それとも平凡な良史として生涯を幸福にすごすか、とうことを考えつづけ、ついに(かならずしも狂にあらず)とまで思うにいたった。
ひとには環境というものがあり、天命ははじめから定まっている。 これはうごかしようもないのに、血気にはやり風雲の中にとびだすことのみ考えているというのは、真の強者ではあるまい。
真の強者の道は自分の天命を知り、みずからの運命に満足することであるかもしれない、というものであった。
【賢候】
「賢候」というこの種類の立役者は、みずから世界観や時勢収拾策をもち、全藩の陣頭に立って、戦国期の荒大名のように直接指揮できる者をいう。
【思想論】
松陰は晩年、「思想を維持する精神は、狂気でなければならない」と、ついに思想の本質を悟るにいたった。
思想という虚構は、正気のままでは単なる幻想であり、大うそにしかすぎないが、それを狂気によって維持するとき、はじめて世をうごかす実体になりうるということを、松陰は知ったらしい。
【時勢の沸騰】
――水戸を継ぐ者は、わが長州ならん。
という気分が、長州藩の連中に濃厚で、結局、彼らのいうとおりに長州が過激攘夷主義の実力本山としてあらたに登場し、攘夷という、狂気の非合理思想の旗をたかだかとかかげて幕末ぎりぎりまで時勢を沸騰させてゆく。
【長井雅楽(うた)】
「長井雅楽」という名前は、この時期の長州人にとって、かがやくような期待とあこがれにつつまれた存在であり、長井のもつ才力と胆略はただ単に、長州藩を時勢の主役にするだけでなく、天下を救いうるものであると思っていた。
【時勢紛糾】
そういう時期、文久元(1861)年、時勢がとほうもなく紛糾した。
日本の国際的公認政府である徳川幕府としては、かつての大老である井伊直弼が桜田門外ノ変ですでに死んでしまっているとはいえ、かれが締結した安政条約を実行せねばならないときにきている。
アメリカをはじめ諸列強に対して港を開くことである。開国であった。
が、幕府にとって悲劇的な、もしくは喜劇的なつらさは国内世論が攘夷鎖国であることであった。
「神国を夷人の靴で汚すな」という一時代すぎたあとからみれば異常としかいいようのない論理と狂気が国内を轟々と沸騰させている。
【事態紛糾】
要するに、日本は二つにわれている。やむなく外国に対し門戸を開こうという江戸と、外には攘夷、内には鎖国という妥協のないスローガンをかかげている京都とである。
その京を足場に、長州藩と薩摩藩という二大外様が、時勢の主舞台におどり出ようとしていた。
が、事態が紛糾しきっているために、「もうなにがなんであるか、わからなくなった」といって、この時期、萩城でぼう然としていたのは長州藩士毛利敬親であった。
【時勢に対する緊張の欠如】
この時期の幕府というのは、やることなすこと間が抜けている。
上海への使節派遣というのは、貿易調査が目的であった。(中略) 港をひらいて貿易をするについてどういう貿易実務をするべきかがわからず、それを上海において見学しようというのである。
が、その人選の点で、時勢に対する緊張が欠けていた。
そういう趣旨であれば、徳川国家の将来の貿易行政をとりしきるような人材をえらぶべきであるのに、(中略) なんの志もないその日暮らしの小役人をずらりとえらんでしまった。
(中略) かれら諸藩の士はこの上海ゆきを契機にそれぞれの藩に重大な影響をあたえ、その影響はのちに明治期の日本にまでおよぶとまでいえるのだが、かんじんの幕府だけは札つきといっていい無能人をそろえ、千歳丸に乗せた。
【攘夷という狂気】
「攘夷。あくまでも攘夷だ」といったのは、攘夷というこの狂気をもって国民的元気を盛りあげ、沸騰させ、それをもって大名を連合させ、その勢いで幕府を倒すしか方法がないと知ったのである。
【議論家から革命家へ】
晋作が議論家から革命家になるのは上海からの帰国後であるといっていい。この時期からのかれの行動は、後年、伊藤博文が晋作の碑に碑銘をきざんだように、
ーー動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し。
というようになる。
【出典】「合本 世に棲む日日(一)~(四)」「世に棲む日日」